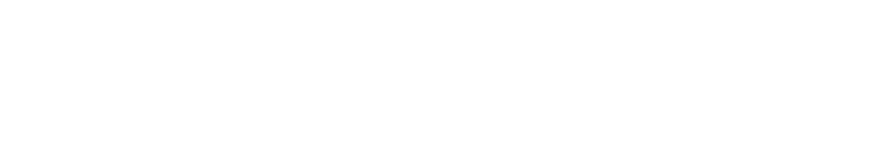こんにちは。
摂津本山駅スグに医院を構える「医療法人 岡田歯科」院長の岡田です。
こちらのブログではお問い合わせやご相談の多い「インプラント治療」について詳しくお伝えしていきます。
今回はインプラントの歴史についてお話ししていきます。
日本のインプラントの歴史
 日本でインプラント治療が始まったのは1978年頃で、現在のチタン製インプラントが日本に普及し始めたのは1983年以降です。
日本でインプラント治療が始まったのは1978年頃で、現在のチタン製インプラントが日本に普及し始めたのは1983年以降です。
しかし欧米では1965年頃に初めてチタン製のインプラント治療が行われ、2006年までの約40年間、問題なく機能したとされています。
つまりインプラント治療において我が国は、欧米から約20年の遅れをとっているのです。
何故日本でのインプラント治療は遅れたのか
日本のインプラント治療が行われるようになった当時は、人工サファイア製でした。チタンのように骨と結合できず、周囲の歯に固定しなければならなかったり、インプラントが折れてしまったりと「インプラントは危険」という悪いイメージが先行。
1983年頃に、当時東京歯科大学の助教授であった小宮山弥太郎先生が、インプラント発祥の地であるスウェーデンのブローネマルク博士のところに留学し、日本に現在のインプラントの考え方やチタン製インプラントを使用した手術方法を持ち帰ったものの、インプラントのイメージ改善は難しかったため、小宮山先生は大学病院を辞職。1990年に自ら日本初のインプラントセンターを開業し、チタン製インプラントの普及のため尽力されています。
未熟な、日本のインプラント教育
日本でもチタン製インプラント手術は、近年かなり普及し、諸外国での手術成功率と日本での手術成功率に、差もなくなってきています。
しかし大学での講義がスタートしたのは2000年初め頃。実習レベルのカリキュラムが導入されたのは2010年以降。
つまり40代以上の歯科医師は大学在学中に講義すら受講していない可能性もあるのです。
そういった年代の歯科医師がインプラントを学ぶのは、インプラントを販売するメーカーや歯科の先生が主催する勉強会。
しかし半年~1年間の研修の受講後に認定を受けられるものもあれば、1~2日間程度で認定が出るものもあり、「週末に講座を受けて、休み明けから手術を担当する」といったケースも十分起こりえるのです。
インプラントの失敗例があるのは、こういった教育環境が起因しているのでしょう。
歯科医師の実績を確認することが重要

歯科医院の看板を見ただけでは歯科医師がどんな勉強をし、どんな実績を積んできたのかはわかりません。
インプラント治療を検討される際は、事前にホームページを確認したり、医師に相談をされることが重要。お口の健康は日々の生活に大きく影響します。歯科医院選びは慎重に行いましょう。